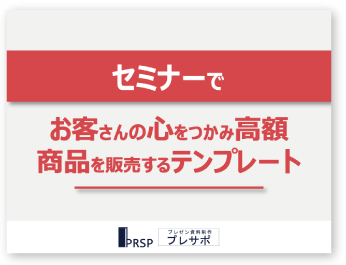ビジネスの現場において、新しいプロジェクトの立ち上げ、新商品の開発、業務改善の実行など、何か新しいことを始める際には、その計画の全体像と価値を関係者に伝え、承認や協力を得るための「企画書」が不可欠です。
しかし、「いざ企画書を作ろうとしても、何から手をつけていいか分からない」「時間をかけて作成したのに、内容がまとまらず、相手に意図が伝わらなかった」
という経験を持つ方も多いのではないでしょうか。実は、人を動かし、プロジェクトを成功に導く優れた企画書のほとんどは、パソコンに向かって書き始める前の「事前準備」の段階で、その出来栄えがほぼ決まっています。
目的が曖昧なまま、あるいは情報が不十分なまま書き進めても、論理的で説得力のある企画書にはなりません。
この記事では、企画書作成の根幹をなす「事前準備」に焦点を当て、具体的に何をすべきなのか、どのような情報を集め、整理する必要があるのかを順序立てて解説します。
さらに、企画書に盛り込むべき必須の内容や、思考を整理し、説得力を高めるための便利なフレームワーク、そして作成時のポイントまで、網羅的にご紹介します。
目次
そもそも企画書とは?
企画書とは、組織や個人が抱える課題を解決したり、目標を達成したりするための新しいアイデア(企画)を具体的に示し、その実行を促すための文書です。主に社内の上司や経営層、関連部署の担当者といった内部の関係者に対して提出され、その企画の承認(決裁)を得ることを目的とします。
企画書には、なぜその企画が必要なのかという「背景」、何を達成したいのかという「目的」、そして、どのように実行するのかという「具体的な方法」や「必要な予算・人員」などが論理的にまとめられます。
ここで、よく混同されがちな「提案書」との違いを明確にしておきましょう。企画書が主に「社内向け」の文書であるのに対し、提案書は主に「社外向け」、つまり顧客や取引先に対して提出される文書です。
提案書は、顧客が抱える課題に対し、自社の製品やサービスを用いてどのように解決できるかを提示し、契約の受注を目指すことを目的とします。
つまり、企画書は「アイデアを実現するための承認を得る」ための文書、提案書は「自社のサービスを販売するための契約を得る」ための文書、という点で目的と対象者が異なります。
ただし、使われる分析手法や論理構成には共通点も多く、質の高い企画書を作成するスキルは、そのまま説得力のある提案書作りにも活かされます。
企画書を書く前の事前準備
優れた企画書を作成するためには、いきなりパワーポイントなどを開いてスライドを作り始めるのではなく、入念な事前準備を行うことが極めて重要です。この段階で企画の骨子を固めておくことで、手戻りがなくなり、論理一貫した説得力のある文書を効率的に作成できます。
企画の方向性を考える
まず、最初に行うべきは企画全体の「目的」と「ゴール」を明確にすることです。「何のために、この企画を実行するのか?」という根本的な問いに、一言で答えられるようにしましょう。
例えば、「新商品の投入によって、3年後に市場シェアを10%拡大する」「新しい業務システムを導入し、部署の残業時間を月平均20%削減する」といった具体的なレベルまで目的を掘り下げます。
この目的が曖昧なままでは、以降の作業全ての軸がぶれてしまいます。企画の方向性を定めることは、これから進むべき道の地図を描く第一歩です。この企画が会社や部署のどのような課題を解決し、どのような利益をもたらすのかを明確に定義することが、企画書全体の説得力を支える土台となります。
ターゲットを設定する
次に、この企画書を「誰に」読んでもらい、「誰の」承認を得る必要があるのかというターゲット(読み手)を具体的に設定します。企画書の最終的な決裁者は社長なのか、それとも担当役員や部長なのか。また、決裁には至らないまでも、企画の実行に協力を仰ぐ必要がある関連部署の担当者などもターゲットに含まれます。
ターゲットによって、企画書に盛り込むべき情報や、強調すべきポイントは大きく異なります。例えば、経営層に向けては、事業全体への貢献度や投資対効果(ROI)といった経営的な視点が重要になります。
一方、現場の担当者に向けては、その企画が日々の業務にどう影響するのか、どのようなメリットがあるのかといった、より具体的な情報が求められます。ターゲットの役職や関心事、知識レベルを想定し、その相手に「刺さる」内容と構成を考えることが、企画を通すための重要な戦略です。
企画の概要を書き出す
目的とターゲットが定まったら、本格的な資料作成に入る前に、企画の全体像を文章で書き出してみましょう。これは「コンセプトシート」や「企画メモ」とも呼ばれるもので、A4用紙1枚程度にまとめるのが理想です。
この段階では、綺麗な体裁にこだわる必要はありません。箇条書きやマインドマップなどを活用しながら、現状の課題、企画の目的、具体的な施策、期待される効果、必要な予算やスケジュールといった要素を、思いつくままに書き出していきます。
この作業を通じて、頭の中にある漠然としたアイデアが整理され、企画全体の論理的なつながりや、情報が不足している部分が明確になります。ここで作成した概要が、後の企画書全体の骨格となります。
企画書を作成するためのツールを選定する
企画の骨子が固まったら、最後に、企画書をどのようなツールで作成するかを決定します。ビジネスシーンで最も一般的に使用されるのは、Microsoft PowerPoint(パワーポイント)でしょう。図やグラフを多用し、視覚的に分かりやすい資料を作成するのに適しており、プレゼンテーションでの使用も想定されています。
一方で、より詳細な文章やデータを示す必要がある場合は、Microsoft Word(ワード)が適していることもあります。また、GoogleスライドやGoogleドキュメントといったクラウドベースのツールは、複数人での共同編集が容易であるというメリットがあります。
企画書の内容や提出先の文化、プレゼンの有無などを考慮し、最も適したツールを選定します。ツールの特性を理解し、その機能を最大限に活用することが、分かりやすく、説得力のある企画書作りにつながります。
企画書にまとめるべき内容
事前準備で固めた骨子を基に、企画書の具体的な中身を作成していきます。ここでは、一般的な企画書に盛り込むべき7つの必須項目について、その役割と書くべき内容を解説します。これらの要素を論理的な順序で構成することが、説得力のあるストーリーを生み出します。
エグゼクティブサマリー
エグゼクティブサマリーとは、企画書全体の要約です。特に、多忙な経営層や決裁者に向けて、企画書の冒頭で、その企画の核心を1ページ程度で簡潔に伝えます。この部分を読んだだけで、企画の全体像と最も重要なポイント(課題、目的、解決策、効果、必要な投資など)が理解できるようにまとめるのが理想です。
決裁者は、日々多くの書類に目を通しているため、詳細な本文を読み込む時間がない場合も少なくありません。冒頭のエグゼクティブサマリーで興味を引き、「この企画は検討する価値がある」と思わせることができなければ、その先を読んでもらえない可能性すらあります。企画書全体の魅力を凝縮した、いわば「予告編」のような重要な役割を担います。
現状分析
次に、この企画がなぜ今必要なのか、その背景となる現状の課題や問題点を具体的に示します。ここでは、客観的なデータや事実に基づいて分析を行うことが極めて重要です。「なんとなく売上が落ちている」といった主観的な表現ではなく、「過去3年間の同四半期と比較して、主力商品Aの売上が20%減少している」というように、具体的な数値を用いて問題の深刻さを提示します。
市場の動向、競合の状況、自社の弱みといった外部環境・内部環境の分析結果を示し、「このまま放置すれば、さらに深刻な事態に陥る」という危機感を読み手と共有します。この現状分析に説得力があるほど、後続の解決策(企画内容)の必要性が際立ちます。後述する3C分析やSWOT分析といったフレームワークを活用すると、体系的で説得力のある分析が可能です。
企画の目的と全体像
現状分析で明らかになった課題に対し、この企画が何を目的としており、どのような状態を目指すのかを明確に定義します。
ここでの目的は、現状分析で示した課題と表裏一体の関係にあるべきです。例えば、「主力商品Aの売上20%減少」という課題に対しては、「テコ入れ策として新機能を搭載した商品A’を投入し、1年後までに売上を前年比15%増まで回復させる」といった具体的な目的を設定します。
また、企画の全体像(コンセプト)を一言で表現するキャッチフレーズのようなものを提示するのも効果的です。企画の目指す方向性をシンプルに示すことで、読み手の理解を助け、関係者間の認識を統一することができます。
企画の具体的な内容
企画の目的を達成するために、「具体的に何を行うのか」を詳細に説明する、企画書の中核部分です。誰が、いつ、どこで、何を、どのように行うのかを、読み手が具体的にイメージできるよう、分かりやすく記述します。
この部分を構造的に考える際に役立つのが、「CTPT」というフレームワークです。
・Concept(コンセプト): 企画の基本的な概念や考え方。誰に、どのような価値を提供するのか。
・Target(ターゲット): 企画の対象となる顧客層や、施策の対象者。
・Process(プロセス): 企画を実行するための具体的な手順や流れ。
・Tool(ツール): 企画の実行に必要な道具やシステム、媒体。
これらの要素に沿って具体策を整理することで、抜け漏れがなく、体系だった説明が可能になります。例えば、新商品の販促企画であれば、コンセプトは「忙しい現代人のための時短調理キット」、ターゲットは「30代の共働き世帯」、プロセスは「SNSでのインフルエンサーマーケティングとWeb広告の展開」、ツールは「InstagramとGoogle広告」といった形で具体化していきます。
実施までのスケジュール
企画の承認後、いつまでに何を行うのかを具体的なスケジュールとして提示します。ガントチャートなどを用いて、タスクの開始日と終了日、担当者、各タスク間の依存関係などを視覚的に示すと、非常に分かりやすくなります。
現実的に実行可能な、無理のないスケジュールを引くことが重要です。マイルストーン(中間目標)を設定し、各段階での進捗を確認できるような計画にすることで、プロジェクト管理が容易になり、読み手に安心感を与えることができます。
このスケジュールが曖昧だと、企画全体の実現性が疑われてしまうため、慎重に作成する必要があります。
収支計画
企画を実行するために、どれくらいの費用(コスト)が必要で、それによってどれくらいの収益(リターン)が見込めるのかを、具体的な金額で示します。
コストには、人件費、開発費、広告宣伝費、設備投資費など、企画に関わる全ての費用を洗い出し、積み上げ式で算出します。
一方、リターンについては、売上の増加額やコスト削減額などを、その算出根拠と共に示します。希望的観測ではなく、現実的で達成可能な数値を提示することが信頼を得る上で重要です。
投資対効果(ROI)や、投資額をいつまでに回収できるか(回収期間)なども併せて示すと、経営層は投資判断がしやすくなります。この収支計画の精度が、企画の承認を左右する最も重要な要素の一つとなります。
企画のゴール
最後に、この企画が成功した暁に、どのような状態になっているのか、改めて「ゴール」を示して締めくくります。これは、冒頭で設定した「目的」を、より具体的で魅力的な形で再提示するものです。
「この企画により、業界内での当社のブランドイメージは飛躍的に向上し、顧客満足度No.1の地位を確立できると確信しています」というように、企画の成功がもたらすポジティブな未来像を力強く描くことで、読み手の感情に訴えかけ、承認への最後の一押しをします。
企画全体を振り返り、その意義と価値を再確認させる、重要なクロージングの役割を果たします。
企画書を作成する際に役立つフレームワーク
企画書の事前準備や内容の整理において、ビジネスフレームワークを活用することは非常に有効です。思考の整理を助け、論理の抜け漏れを防ぎ、説得力を高めることができます。ここでは、代表的な3つのフレームワークを紹介します。
6W2H
6W2Hは、情報を整理し、計画の要素を明確にするための基本的なフレームワークです。企画の全体像を網羅的にチェックする際に役立ちます。
| 要素 | 英語 | 質問 |
| Why | なぜ | なぜこの企画を行うのか?(目的・背景) |
| What | 何を | 具体的に何をするのか?(企画内容) |
| Who | 誰が | 誰が担当するのか?(体制) |
| Whom | 誰に | 誰を対象とするのか?(ターゲット) |
| When | いつ | いつ行うのか?(スケジュール) |
| Where | どこで | どこで実施するのか?(場所・市場) |
| How | どのように | どのような方法で実行するのか?(手段) |
| How much | いくらで | いくらかかるのか?(費用) |
これらの8つの要素に沿って企画内容を自問自答することで、計画の具体性が増し、考慮すべき点が明確になります。
3C分析
3C分析は、主に事業環境を分析するためのフレームワークで、「現状分析」のパートで特に有効です。自社を取り巻く環境を3つのCから分析し、成功要因を見つけ出します。
| 要素 | 英語 | 分析内容 |
| Customer | 顧客・市場 | 市場規模、成長性、顧客ニーズ、購買行動はどうか? |
| Competitor | 競合 | 競合他社はどこか?その強み・弱み、戦略は何か? |
| Company | 自社 | 自社の強み・弱み、経営資源、ブランド力はどうか? |
市場と競合の状況を把握した上で、自社の立ち位置を客観的に評価することで、自社が勝てる領域や、取るべき戦略の方向性が見えてきます。
SWOT分析
SWOT分析は、内部環境と外部環境を「強み」「弱み」「機会」「脅威」の4つの要素で評価し、戦略立案に役立てるフレームワークです。3C分析の結果を、この4象限に落とし込んで整理することが多いです。
| 内部環境 | 外部環境 | |
| プラス要因 | Strength(強み) ・高い技術力 ・強力なブランド | Opportunity(機会) ・市場の拡大 ・法改正による追い風 |
| マイナス要因 | Weakness(弱み) ・価格競争力の低さ ・人材不足 | Threat(脅威) ・新規競合の参入 ・景気の悪化 |
この分析から、「自社の強みを活かして機会を掴むには?(積極化戦略)」や「自社の弱みを克服し、脅威を回避するには?(差別化戦略)」といった、具体的な戦略オプションを導き出すことができます。
企画書を作成する際のポイント
内容が固まったら、いよいよ資料として仕上げていきます。どんなに優れた内容でも、伝わらなければ意味がありません。
読み手の理解を助け、説得力を最大化するための6つのポイントを紹介します。
ポイント①客観的な視点を意識する
企画書は、自分のアイデアの素晴らしさを主張するだけの文書ではありません。独りよがりな思い込みや希望的観測を排除し、常に客観的なデータや事実に基づいて論理を展開することが重要です。
売上予測や市場分析などでは、信頼できる第三者機関の調査データを引用するなど、根拠を明確に示すことで、企画全体の信憑性が格段に高まります。
ポイント②読みやすさを意識する
企画書は、一目見て内容の骨子が理解できるような、シンプルで分かりやすい構成を心がけるべきです。1つのスライドに情報を詰め込みすぎず、「1スライド=1メッセージ」を原則とします。
専門用語や業界用語の使用は避け、誰が読んでも理解できる平易な言葉を選びましょう。図やグラフ、イラストなどを効果的に活用し、視覚的に訴えることで、読み手の理解を助け、退屈させない工夫も重要です。
ポイント③転換ページを作成する
企画書が長くなる場合、話の節目節目に「アジェンダ」や「中扉」といった転換ページを挿入すると効果的です。
「これまでのまとめ」や「ここからは、具体的な実施計画についてご説明します」といった案内を入れることで、読み手は今、話全体のどの部分にいるのかを把握しやすくなります。これにより、思考が整理され、後の内容への集中力を維持することができます。
ポイント④ページ数をできるだけ絞る
伝えたいことが多いと、つい企画書は分厚くなりがちです。しかし、多忙な決裁者にとって、分厚い企画書は読む気力を削ぐ原因になります。企画の骨子に関わらない余分な情報は大胆に削ぎ落とし、できるだけコンパクトにまとめることを心がけましょう。
詳細なデータや補足資料は、巻末に「参考資料」として添付する形にすれば、本編をすっきりとさせることができます。伝えたいことの量ではなく、伝わる情報の質を重視しましょう。
ポイント⑤具体的な数値目標を提示する
企画の目的やゴールを示す際には、「売上を増やす」「業務を効率化する」といった曖昧な表現ではなく、具体的な数値目標を提示することが不可欠です。
「半年で売上を1,000万円向上させる」
「導入後3ヶ月で、作業時間を一人あたり月5時間削減する」
というように、測定可能な目標を設定します。これにより、企画の達成度が客観的に評価できるようになり、計画の具体性と実現可能性に対する信頼が高まります。
ポイント⑥文字フォントは統一する
資料全体のデザイン的な一貫性も、読みやすさに影響します。特に文字フォントは、企画書全体で統一するのが基本です。複数のフォントが混在していると、雑然とした印象を与え、読み手の集中を妨げます。
ビジネス文書では、Windows環境であれば「メイリオ」や「游ゴシック」、Mac環境であれば「ヒラギノ角ゴシック」といった、視認性の高いゴシック体を使用するのが一般的です。フォントサイズや色使いにも一貫したルールを設け、洗練された印象を与えることを目指しましょう。
マーケティング資料作成方法でも何かヒントが得られるかもしれません。
関連記事:マーケティング資料の作り方やポイントを解説
優れた企画書には優れた事前準備が不可欠である
優れた企画書とは、単に見た目が美しい資料のことではありません。明確な目的に基づき、客観的な事実とデータによって裏付けられた論理的なストーリーが、読み手の心を動かし、行動を促します。そして、その根幹をなすのが、企画書を書き始める前の、深く、緻密な思考と準備のプロセスなのです。
しかし、質の高い企画書をゼロから作成するには、情報収集、市場分析、戦略立案、収支計画の策定、そして分かりやすい資料への落とし込みといった、多岐にわたるスキルと膨大な時間を要するのも事実です。
「日々の業務が忙しく、資料作成に十分な時間を割けない」「より専門的で、説得力のある資料を作成したいが、ノウハウが足りない」 もし、このようなお悩みをお持ちでしたら、ぜひ一度、私たちNull Japan株式会社が提供するプレゼン・営業資料作成代行サービス「プレサポ」にご相談ください。
「プレサポ」では、経験豊富なコンサルタントとデザイナーが、お客様の目的や伝えたい内容を丁寧にヒアリングし、論理構成からデザインまで、高品質な資料をワンストップで作成いたします。お客様は、資料作成にかかる膨大な時間から解放され、本来注力すべきコア業務に集中することができます。説得力のある企画書・提案書で、ビジネスを次のステージへ進めるお手伝いをさせていただきます。
誰でも簡単にきれいなプレゼン資料が作れる
↓↓↓

.png)